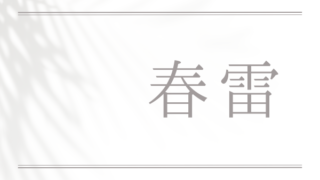 季語
季語 春の季語「春雷」の読み方や意味、例文を徹底解説!
春が訪れると、自然界にはさまざまな変化が現れます。草木が芽吹き、花が咲き、温かい風が吹く中で、時折響き渡る雷の音に驚いたことはありませんか?この雷は「春雷(しゅんらい)」と呼ばれ、春の訪れを象徴する美しい季語の一つです。本記事では、「春雷」...
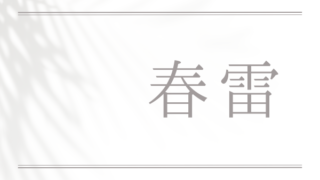 季語
季語  季語
季語 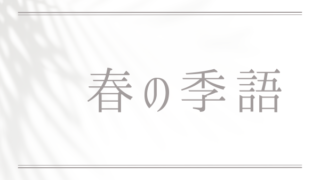 季語
季語  季語
季語 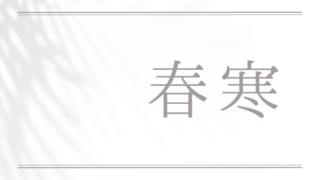 季語
季語 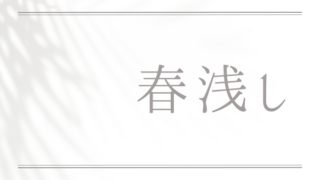 季語
季語 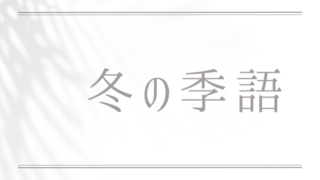 季語
季語  季語
季語 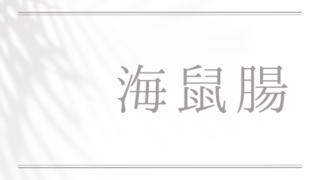 季語
季語  季語
季語